 Art Garfunkel / Songs From A Paret To A Child
Art Garfunkel / Songs From A Paret To A Child
■Art Garfunkelがわが息子Jamesのために作ったアルバムSongs From A Paret To A Child。このようなタイプの音は大体が「どうだい、うちの子可愛いだろー」的な嫌らしさが見え隠れするのだが、さすがアーティはエンターティンメントのプロに徹していて、聞くもの誰にでも楽しめるアルバムを作ってくれている。
■一曲目のWho's Gonna Shoe Your Pretty Little Feetの素朴なトラディショナルな雰囲気にやられてしまうこのアルバム。優しく力強いアートの歌声はすでに「天使の歌声」とは程遠いが、そんな自分の力量に相応しい歌をセレクトしていて、老いを全然感じさせない。若い頃のような張り上げる壮大なバラードが少ない分、軟らかいメロディやアレンジが目立ち、とても聴きやすい内容になっている。
■選曲もCAT STEVENSの「MORNING HAS BROKEN」やLOVIN' SPOONFULの「DAYDREAM」、ダンボで有名な「BABY MINE」、BEATLESの「I WILL」など。それらの名曲を新緑のような温かく爽やかな音の涼風に仕上げている。たった一曲だけGood Luck Charmで8歳くらいなのか?のJamesくんがメインボーカルを取っているが、これがまた上手い。やはり血筋なのか、それとも父親による相当なボイトレがあったのか、普通に子供番組でかかりそうな曲になっている。
![]()
![]()
■試聴・購入はロゴをクリックしてね。

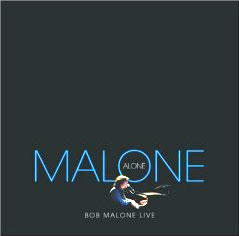

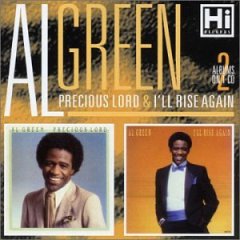





 Artie Traum、Chris Shaw、Tom Aksterns / Big Trout Radio
Artie Traum、Chris Shaw、Tom Aksterns / Big Trout Radio Creedence Clearwater Revival / Chronicle
Creedence Clearwater Revival / Chronicle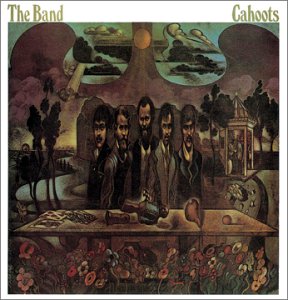
 Blind Blake / All The Published Sides
Blind Blake / All The Published Sides
 Armando Trovaioli / Sesso Matto(OST)
Armando Trovaioli / Sesso Matto(OST) Armando Trovaioli / Italian Style Comedies: Film Music
Armando Trovaioli / Italian Style Comedies: Film Music  Cherrelle / High Priority
Cherrelle / High Priority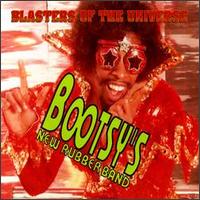 Bootsy Collins / Blasters of the Universe
Bootsy Collins / Blasters of the Universe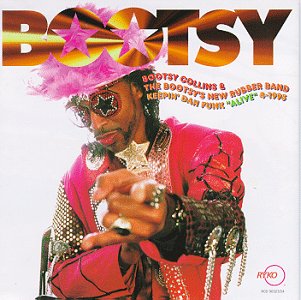 Bootsy Collins /Keepin' Dah Funk "ALIVE"
Bootsy Collins /Keepin' Dah Funk "ALIVE" Bootsy Collins / What's Bootsy Goin'?
Bootsy Collins / What's Bootsy Goin'? Circe Link / More Songs! from Circe Link
Circe Link / More Songs! from Circe Link  あがた森魚 / 日本少年
あがた森魚 / 日本少年 相曽晴日 / トワイライトの風
相曽晴日 / トワイライトの風  クレイジーケンバンド / グランツーリズモ
クレイジーケンバンド / グランツーリズモ Babs Gonzales / 1947-1949
Babs Gonzales / 1947-1949 吾妻光良&The Swinging Boppers / Squeezin' and Blowin'
吾妻光良&The Swinging Boppers / Squeezin' and Blowin' Chevalier Brothers / Live And Still Jumping
Chevalier Brothers / Live And Still Jumping The Cats & The Fiddle / Killin' Jive 1939-1940
The Cats & The Fiddle / Killin' Jive 1939-1940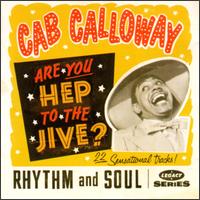 Cab Calloway / Are You Hep To The Jive?
Cab Calloway / Are You Hep To The Jive?
 Booker T. & The MG's / The Very Best Of Booker T. & The MG's
Booker T. & The MG's / The Very Best Of Booker T. & The MG's 
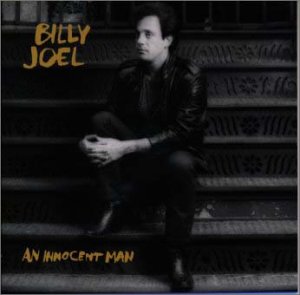
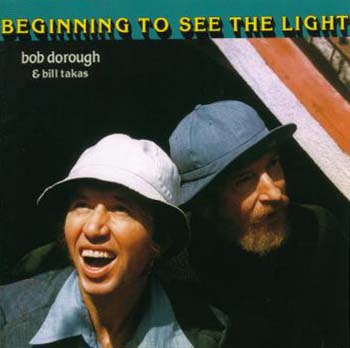 Bob Dorough / Beginning To See The Light
Bob Dorough / Beginning To See The Light





 Bob Marley and The Wailers / Legend
Bob Marley and The Wailers / Legend
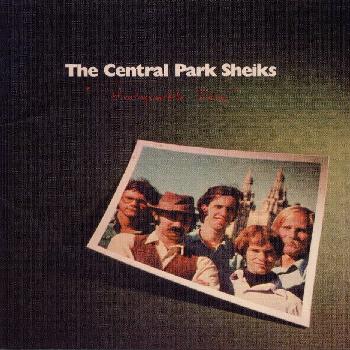
 Asylum Street Spankers / Hot Lunch
Asylum Street Spankers / Hot Lunch

