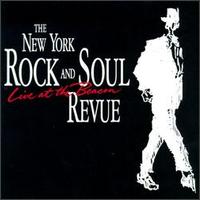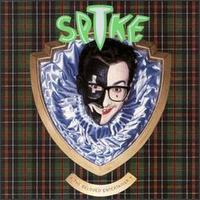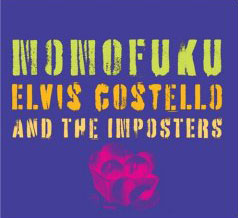 Elvis Costello and the Imposter / MOMOFUKU
Elvis Costello and the Imposter / MOMOFUKU
■「百福」ってなんやねんイギリス人が興味本位で極東の他人の名前をタイトルにしたんか、ひとの文化をめずらしがりやかって。アナログのみの発売? どうせ話題作りで後でCD出すんだから、ベテランが格好つけんでもいいやん…というのがこのアルバムの発売情報を聞いた時の第一印象、はっきりいって「コステロも終わったか」という感じで試聴すらしなかった。(安藤百福はインスタント・ラーメンの発明者)
■自分にとってコステロは八割方は「当たり」なのだが「ペインテッド・フロム・メモリー
」「ジュリエットレターズ」のような二度聴く気にならない作品が時々あるので、情報だけでそういう部類の作品として片付けてしまった(レターズも聴く人によっては名盤だろう、僕がコステロに期待する作品でないだけだ、念のため)。
■しかしネットのレビューで「コステロらしい」「昔に戻った」というものをちらほら見かけるようになった。レビュワーがいつの頃をもって「昔」とか「らしい」と表現しているのかわからなかったが、なんとなく「スパイク」や「マイティ・ライク・ア・ローズ」のころのテイストなのかなと思い、多少前向きになってAmazonのカートにいれたのが7月初め頃、そしてこの度8月に入ってようやく入手した。
■ずっと聴いているアーティストなのに本当に出会うまで時間がかかった2008年発売のエルビスコステロの新譜MOMOFUKUはあろうことか初期のアトラクションズとのサウンドを彷彿させるチープで荒削りで怒りに満ち溢れたサウンドだった。
■デビューから30年を経てもこのサウンドとテンションに戻れる、そこがコステロのすごいところなのだろう。アナログ先行発売も話題作りではなく当時の気持ちで聴いて欲しかったのだということが聴いているうちにわかってきた。ごめんなデクラン、あんたはやっぱりヒーローだよ。必聴。
![]()
![]()
■試聴・購入はロゴをクリックしてね。
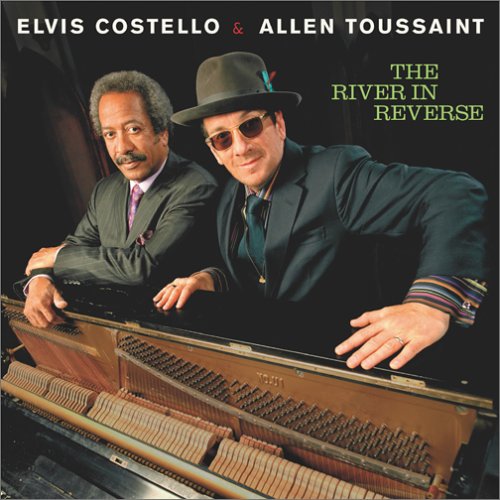
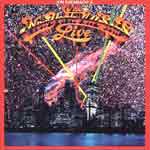
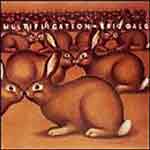
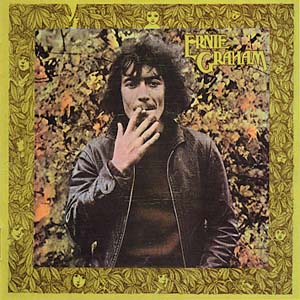
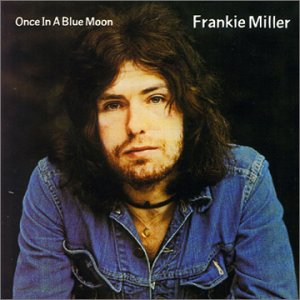
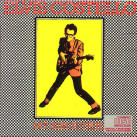

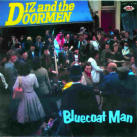
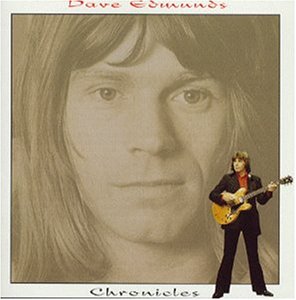
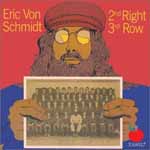 Eric Von Schmidt / 2nd Right 3rd Row
Eric Von Schmidt / 2nd Right 3rd Row The Costello Show / King Of America
The Costello Show / King Of America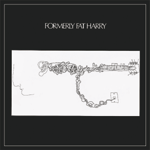
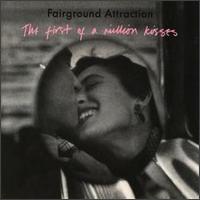
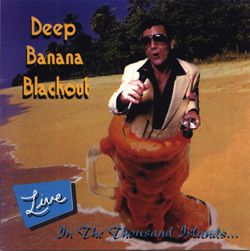 Deep Banana Blackout / Live In The Thousand Islands...
Deep Banana Blackout / Live In The Thousand Islands...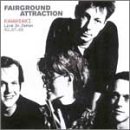 Fairground Attraction / Kawasaki Live In Japan 02.07.89
Fairground Attraction / Kawasaki Live In Japan 02.07.89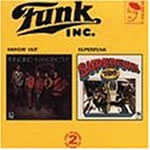
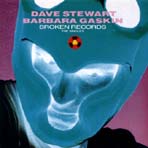 Dave Stewart & Barbara Gaskin / The Singles
Dave Stewart & Barbara Gaskin / The Singles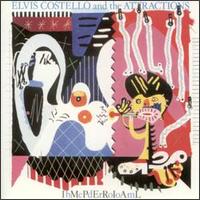
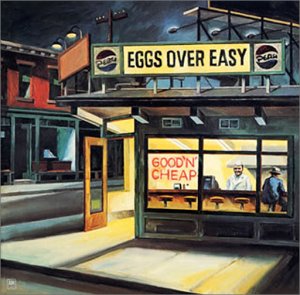
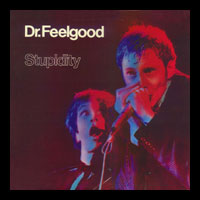
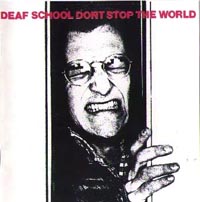 Deaf School / Don't Stop The World
Deaf School / Don't Stop The World
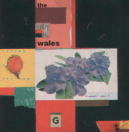
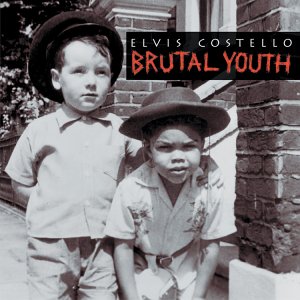 Elvis Costello / Brutal Youth
Elvis Costello / Brutal Youth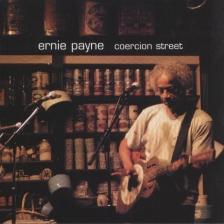 Ernie Payne / Coercion Street
Ernie Payne / Coercion Street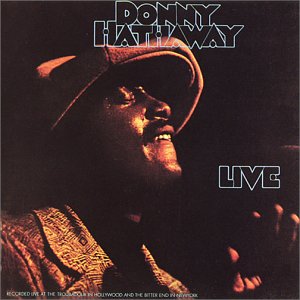 Donny Hathaway / Live
Donny Hathaway / Live 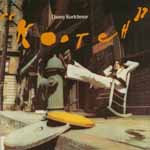
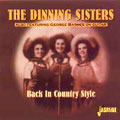 The Dinning Sisters / Back In The County Style
The Dinning Sisters / Back In The County Style Django Reinhardt / Japanese Planet Jazz Buget Collection
Django Reinhardt / Japanese Planet Jazz Buget Collection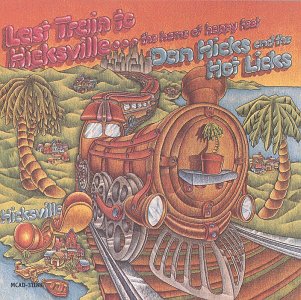 Dan Hicks and the Hot Licks / Last Train To Hicksville...The Home Of Happy Feet
Dan Hicks and the Hot Licks / Last Train To Hicksville...The Home Of Happy Feet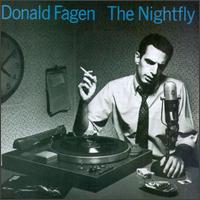 Donald Fagen / The Nightfly
Donald Fagen / The Nightfly