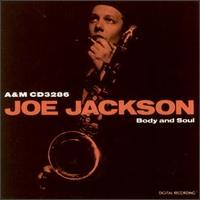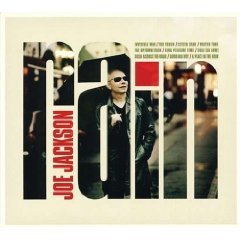 Joe Jackson / Rain
Joe Jackson / Rain
���W���[�W���N�\�����������ĊJ���Ă����̂͂悭�m���Ă������ǁABig World�`Will Power�̗��ꂪ�C�ɐH�킸�y�э��ł����B�N���V�b�N�̐��E�ɍs���Ă��܂����ߋ��̐l�����������̂����ǁA�O��ŏ��S�ɖ߂��āu�{����ҁv�������A����ŁuNight& Day�v�uBody & Soul�v����̉��������Č������炵���B
�����ꂾ���łȂ����̃A���o���͂��炵������I�ł������x�������h�W���[�炵���h����Ȃ̂��B�������������I�ȃs�A�m���A��X�Ɖ̂��グ�鐺���܂���80�N�セ�̂��́A�l�̑�D���������W���[���߂��Ă��Ă��ꂽ�Ƃ��������ł����ς��ł��B�l�b�g�ł̃��r���[���u����v�Ƃ����]���������B
������̓M�^�[���X��3�l�Ґ��Ȃ̂Ńs�A�m���������芬�\�ł���̂��܂����ꂵ���B���̐l�̗₽�����ǐS�n�����s�A�m�̋�������D���ł��B
![]()
![]()
�������E�w���̓��S���N���b�N���ĂˁB
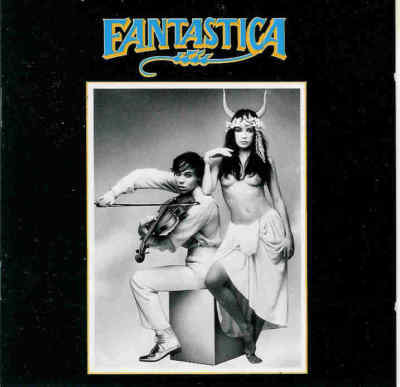
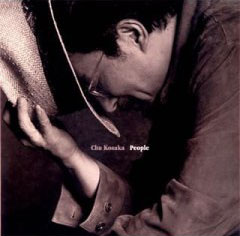
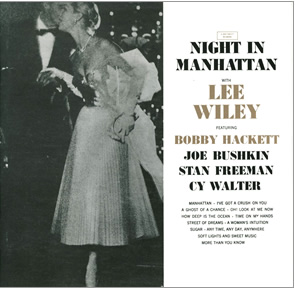
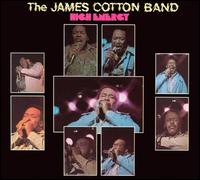
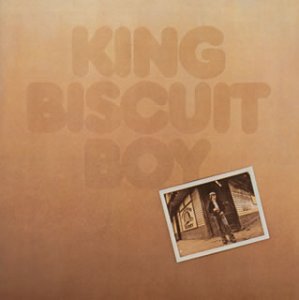


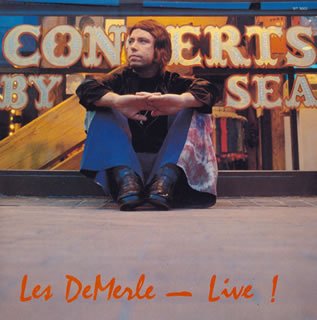
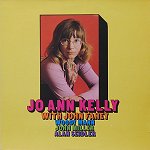
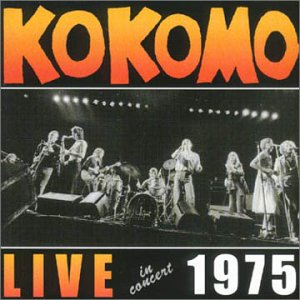
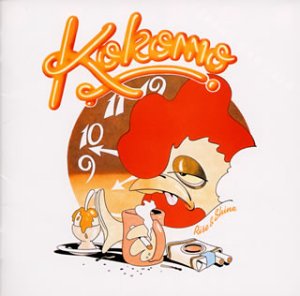

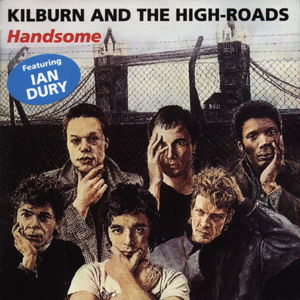
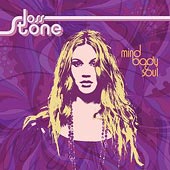 Joss Stone / Mind Body&Soul
Joss Stone / Mind Body&Soul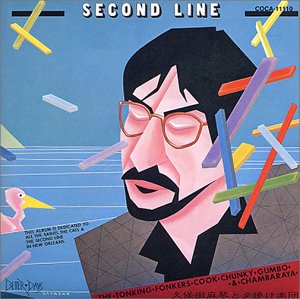 �v�ۓc���ՂƗ[�Ă��y�c / Second Line
�v�ۓc���ՂƗ[�Ă��y�c / Second Line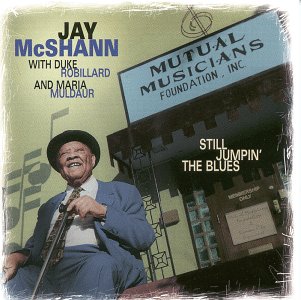
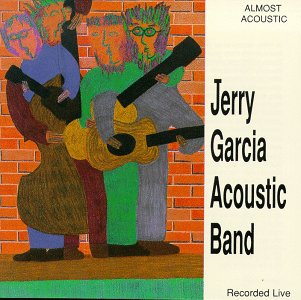 Jerry Garcia Acoustic Band / Almost Acoustic
Jerry Garcia Acoustic Band / Almost Acoustic Little Feat / Dexie Chickin
Little Feat / Dexie Chickin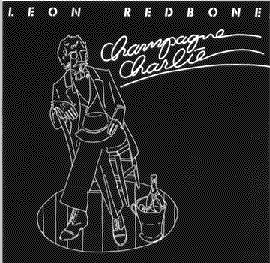 Leon Redbone / Champagne Charlie
Leon Redbone / Champagne Charlie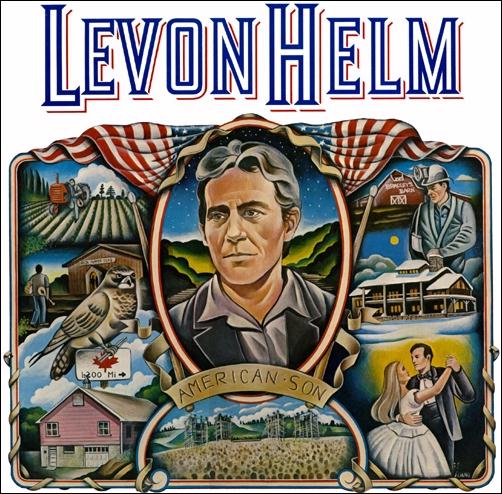
 THE JUMPING JACQUES / AVALON
THE JUMPING JACQUES / AVALON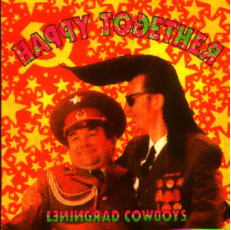 Leningrad Cowboys / Happy Together
Leningrad Cowboys / Happy Together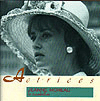 Jeanne�@Moreau / �ނ��� Le Tourbillon
Jeanne�@Moreau / �ނ��� Le Tourbillon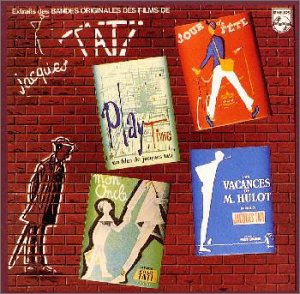
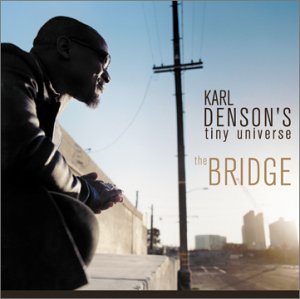 Karl Denson's Tiny Universe / The Bridge
Karl Denson's Tiny Universe / The Bridge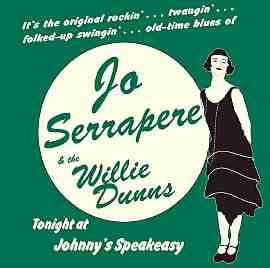 Jo Serrapere & The Willie Dunns /
Jo Serrapere & The Willie Dunns / ����܂y�c / �����̌�������
����܂y�c / �����̌�������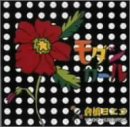 �q�����G�R / ���_���K�[��
�q�����G�R / ���_���K�[��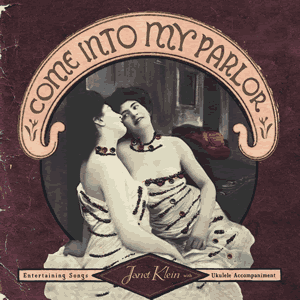 Janet Klein with Ukulele Accompaniment / Come Into My Parlor
Janet Klein with Ukulele Accompaniment / Come Into My Parlor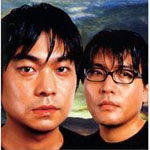 �L�����W / �R
�L�����W / �R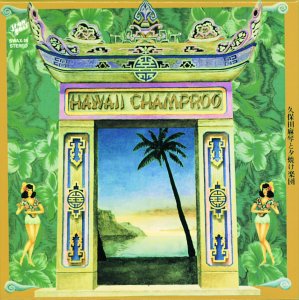 �n���C�`�����v���[ / �v�ۓc���ՂƗ[�Ă��y�c
�n���C�`�����v���[ / �v�ۓc���ՂƗ[�Ă��y�c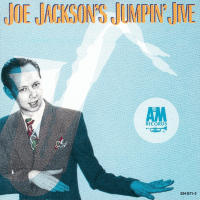
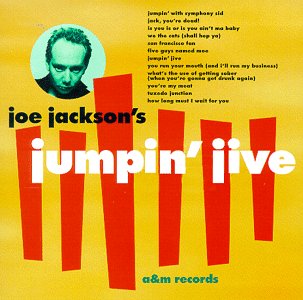 Joe Jackson /
Joe Jackson's Jumpin' Jive
Joe Jackson /
Joe Jackson's Jumpin' Jive 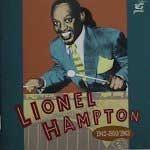 Lionel Hampton / Lionel Hampton 1942-1950/1963
Lionel Hampton / Lionel Hampton 1942-1950/1963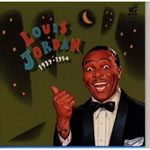 Louis Jordan /Louis Jordan 1939-1954
Louis Jordan /Louis Jordan 1939-1954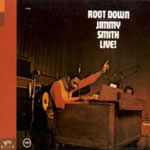

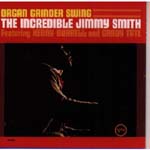 Jimmy Smith / Organ Grinder Swing
Jimmy Smith / Organ Grinder Swing 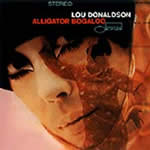 Lou Donaldson / Alligator Boogaloo
Lou Donaldson / Alligator Boogaloo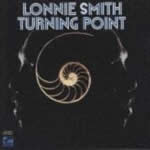
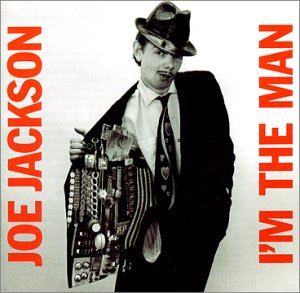
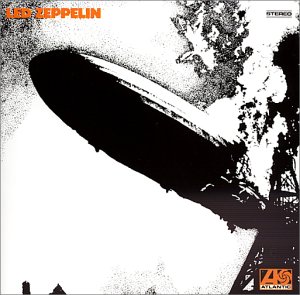 Led Zeppelin / Led Zeppelin
Led Zeppelin / Led Zeppelin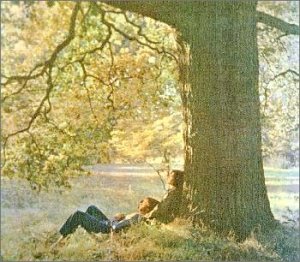 John Lennon / Plastic Ono Band
John Lennon / Plastic Ono Band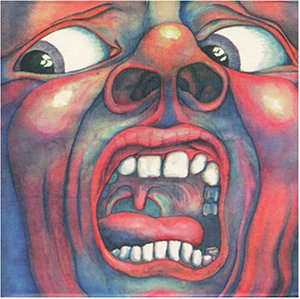 King Crimson / In The Court Of The Crimson King
King Crimson / In The Court Of The Crimson King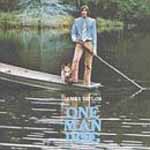 James Taylor / One Man Dog
James Taylor / One Man Dog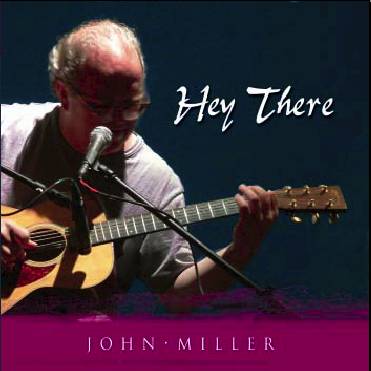
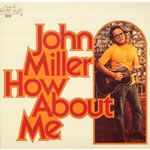 John Miller / How About Me
John Miller / How About Me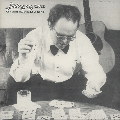

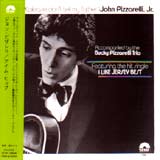 John Pizzarelli Trio / I'm Hip(Please Don't Tell My Father)
John Pizzarelli Trio / I'm Hip(Please Don't Tell My Father)