 Prefab Sprout / Jordan:The Comeback
Prefab Sprout / Jordan:The Comeback
■バンドの中心はPaddy McAloonとプロデューサーのThomas Dolby。優しくって温かい幻想的な音作りはたぶんにDolbyの力なんだろうな。はじめて知ったのは88年のアルバムFrom Langley Park to Memphis。若くて、いかにも古き良きR&Rに憧れているバンドって感じのジャケットだったんだけど、音を聞いたらGreen Gartside(笑)。たまたまScritti PolittiのProvisionが出た当時ではまっていたところもあり即GETだった。彼らの最大の良さはバラードの美しさ。切なくて耽美的でしかし締まりのあるバラードはScrittiPolittiよりも良く出来てるんじゃないかな? とても気に入ったものだ。
■
そして満を持して90年に登場したのがこのアルバムJordan:The Comeback。Jason AnkenyがAll Music Comの批評の中で「役者のいないサウンドトラック」だと言っているが、19曲に及ぶ音の洪水、そしてサンバが出て来たり、ボレロが出て来たりする万華鏡のような雰囲気、あたかも旧約聖書の逸話を彷彿とさせる仰々しい言葉の数々(歌詞の意味はわからんが)は、なにか壮大なストーリーを感じさせる。
■
しかし、言葉がわからない我々には、そんなことよりも音が与える印象の方が大切だ。基本的にはLangley Parkからほとんど変わらない音作り。相変わらずもこもこと幻想的なPOPと切なく可憐なバラードが巧みに混在している。発表から11年経った今考えると、「相変わらず」というよりは集大成だったのではないだろうか?とも思えてくる。84年にSwoonでデビューしてからの6年間のThomas Dolbyとのスタジオワークの集大成。事実この後の唯一のアルバムAndromeda Heights(97発表)にはDolbyは参加していない。メロディメーカーMcAloonと鬼才Dolbyというコラボレーションの完成品としてこのアルバムを考えてみると、まさに美しく完成されているのではないだろうか。
■
Dolbyのバラードはアレンジ等の構成がとてもエキセントリックで美しいがメロディと歌がイマイチだった。そこにMcAloonのメロディと歌を加えた事で、互いに補強しあってこのアルバムが完成したのだとしたらそれはとても素晴らしい事だ。とりあえずとても優しくって愛らしくって美しいアルバムである事にはかわりない。ぼくの中でもPrefabはこのアルバムで満足だ。完成作だと思う。
![]()
■試聴・購入はロゴをクリックしてね。




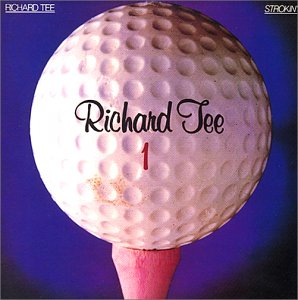


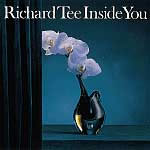


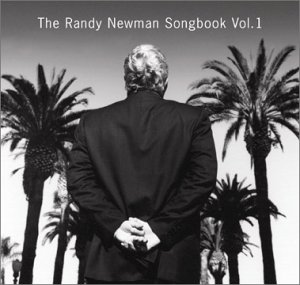 Randy Newman/ Songbook Vol.1
Randy Newman/ Songbook Vol.1 Randy Newman / Ragtime
Randy Newman / Ragtime  Robert Palmer/Sneakin Sally Through The Alley
Robert Palmer/Sneakin Sally Through The Alley

 Randy Newman / Good Old Boys
Randy Newman / Good Old Boys Ry Cooder / Jazz
Ry Cooder / Jazz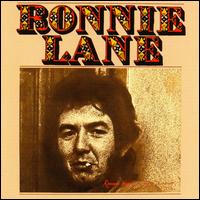
 Ronnie Lane and slim chance / One For The Road
Ronnie Lane and slim chance / One For The Road Peter Hammill / And Close As This
Peter Hammill / And Close As This Ronnie Lane / Anymore For Anymore
Ronnie Lane / Anymore For Anymore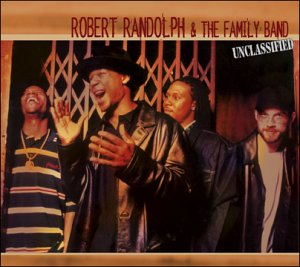 Robert Randolph The Family Band / Unclassified
Robert Randolph The Family Band / Unclassified Parliament / P-Funk Earth Tour
Parliament / P-Funk Earth Tour プア・サウンド・レコード / マタタビジャム
プア・サウンド・レコード / マタタビジャム ピラニアンズ / ピラニアンズ
ピラニアンズ / ピラニアンズ The Ray Ellington Quartet / That's Nice!
The Ray Ellington Quartet / That's Nice!
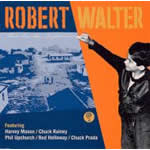
 Prefab Sprout / From Langley Park To Menphis
Prefab Sprout / From Langley Park To Menphis

 Paul Simon / Hearts And Bones
Paul Simon / Hearts And Bones Rufus Wainwright / Poses
Rufus Wainwright / Poses
 Paul Simon / Songs From The Capeman
Paul Simon / Songs From The Capeman Rickie Lee Jones / Girl At Her Volcano
Rickie Lee Jones / Girl At Her Volcano