 S.O.S. Band / Sands of Time
S.O.S. Band / Sands of Time
■高校のころから大好きだったミネアポリスサウンド。ジャム&ルイスプロデュースによる、あのチャカチャカ音です。発表は86年、Janet Jacksonの「Control」とCherreleの「High Priority」、そしてこのアルバムとJam & Lewisが次々に名盤を輩出し、黄金時代を作ったその一枚であります。
■いつ聴いてもゴージャスでダンサブル、おおらかなリズムとひんやり心地いいボーカルがゴールデン80'sに浸らせてくれます。ドライブにも最適。
![]()
![]()
■試聴・購入はロゴをクリックしてね。













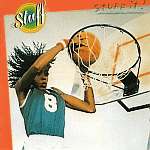




 Stuff / Made In America
Stuff / Made In America

 下田逸郎 / GOLDEN J-POP/ THE BEST
下田逸郎 / GOLDEN J-POP/ THE BEST

 渋さ知らズ / 渋旗
渋さ知らズ / 渋旗 Terri Hendrix / Live
Terri Hendrix / Live Uncle Earl / She Went Upstairs
Uncle Earl / She Went Upstairs UA / Fine Feathers Make Fine Birds
UA / Fine Feathers Make Fine Birds UA / 泥棒
UA / 泥棒 関口和之&砂山オールスターズ / World Hits Of Southern All Stars
関口和之&砂山オールスターズ / World Hits Of Southern All Stars Slim Gaillard & Slam Stewart / Complete Columbia Master Takes
Slim Gaillard & Slam Stewart / Complete Columbia Master Takes
 Soulive / Next
Soulive / Next Templeton Twins / Thrill Ot Like It Was
Templeton Twins / Thrill Ot Like It Was Squeeze / Frank
Squeeze / Frank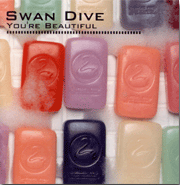
 10cc / 「愛ゆえに」Deceptive Bends
10cc / 「愛ゆえに」Deceptive Bends Tot Taylor / Box-Office Poison
Tot Taylor / Box-Office Poison
 Stan Campbell / Stan Campbell
Stan Campbell / Stan Campbell
 佐野元春 / Someday
佐野元春 / Someday T-Rex / Slider
T-Rex / Slider Speech / Spiritual People
Speech / Spiritual People Stevie Wonder / Key Of Life
Stevie Wonder / Key Of Life
 Uncle Jim's Music / There's a Song In This
Uncle Jim's Music / There's a Song In This 鈴木博文 / 無敵の人
鈴木博文 / 無敵の人 佐藤奈々子 / Tears Of ANGEL〜Best Of
佐藤奈々子 / Tears Of ANGEL〜Best Of さだまさし / 夢回帰線
さだまさし / 夢回帰線
 TITI松村 / ふなのような女
TITI松村 / ふなのような女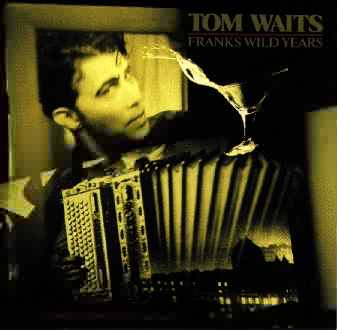 TomWaits / Franks Wild Years
TomWaits / Franks Wild Years Sade / Lovers Rock
Sade / Lovers Rock Steely Dan / gaucho
Steely Dan / gaucho