 Womack & Womack / Family Spirit
Womack & Womack / Family Spirit
■Womack&Womackの夫婦デュオの音を聴いているととても満ち足りた感情が湧いてくる。CecilとLindaの音楽活動は長く、そのデュオワーク以前から栄光に輝いている。Cecilはウーマックブラザーズ(ヴァレンティノズ)のメンバー、つまりBobby Womackの弟だし、Lindaはサム・クックの娘だ。二人はソングライターチームとしてテディペンタグラス・アリーサフランクリン・ウイルソンピケットらをフォローしていた。日本で言えば山下達郎と竹内まりやのデュオみたいなものだろう(笑)。
■正直言って彼ら自身のアルバムは甘い。一曲一曲は丁寧で誠実なつくりをしているが派手さにかける。しかし、その音楽への気持ちは伝わってくる。しっかり耳から、敬意と愛情と信頼が。それがとても気持ち良くって思わず、リピートで聴いてしまう。一曲一曲は心に残りはしないが、満足感が残る。それは91年発表の4枚目のアルバムFamily Spiritの表題曲のアコースティックソウルを聞くだけでわかると思う。ひしひしとその誠実さが伝わって聞いてよかったと思えてくる。
■その満足感はたぶん、互いに相手に対して、言い知れないくらいの信頼と尊敬を持って音楽を作っているからだろう。4枚目のアルバムFamily Spiritのジャケットのお腹を大きくしたLindaとCecilが寄り添う姿を見ているだけで夫婦の絆がしっかり伝わってくる。彼らのアルバムはどれも信頼と尊敬という絆によって出来あがっている。アメリカの夫婦アーティストモノでは珍しいくらいだ。こんな風に夫婦で1歩1歩、手を取り合って歩いていけるなんてとても素敵なことだと思う。
![]()
■試聴・購入はロゴをクリックしてね。


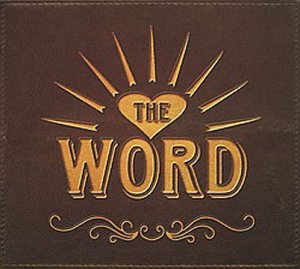 The Word / John Medeski / North Mississippi Allstars / Robert Randolph
The Word / John Medeski / North Mississippi Allstars / Robert Randolph Van Dyke Parks / Discover America
Van Dyke Parks / Discover America
 Van Morrioson / Veedon Fleece
Van Morrioson / Veedon Fleece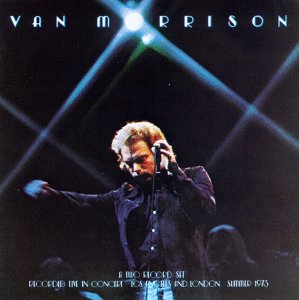 Van Morrison / It's Too Late to Stop Now
Van Morrison / It's Too Late to Stop Now  Van Morrison / Moondance
Van Morrison / Moondance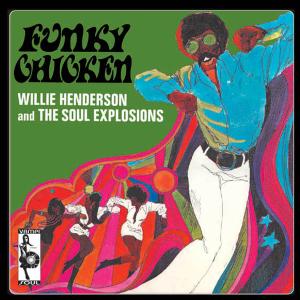 Willie Henderson and the Soul Explosions / Funky Chicken
Willie Henderson and the Soul Explosions / Funky Chicken WYOLICA / who said “La La…”?
WYOLICA / who said “La La…”? XTC / Apple Venus Pt. 1
XTC / Apple Venus Pt. 1 XTC / SKYLARKING
XTC / SKYLARKING
 Willie Colon & Ruben Blades / Siembra
Willie Colon & Ruben Blades / Siembra